「学校、今日行く!」~教育長の学校日記~
たいせつなものが、ここにはある⑨ ~先生と幼児、幼児と幼児、みんなをつなぐ見えない糸~
 |
 |
|---|---|
|
▲「どっちに入っているかな?」「こっちー!」 |
▲創作意欲を高める「材料コーナー」 |
 |
 |
|
▲来てほしい場に、自然と先生の姿があります |
▲「みんなで、先生を助けよう!」サイコロ鬼 |
 |
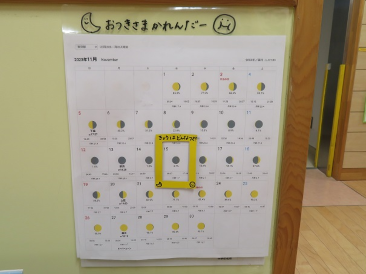 |
|
▲こども会の進み具合をグループ毎に報告します |
▲「今日はどんな月が見られるのかな?」 |
 |
 |
|
▲えらや模様もこだわりがいっぱい(講演より) |
▲みんなで作った「ジンベエザメのぼり」 |
枝川幼稚園を訪問しました。今日は、江東区教育委員会研究協力園として本園が取り組んできた研究成果を発表する、研究発表会の日でした。枝川幼稚園には、5月25日にも訪問させてもらいました。その時の様子も、ぜひ学校日記でご覧ください。
本園の研究主題は、「幼児の豊かな経験につながる行事の在り方」です。現在の幼児は、ほとんどの時間をコロナ禍で過ごしており、地域行事や季節行事をあまり経験できずに入園してきています。この機会に、本園では、これまで園で行ってきた行事や季節行事に関わる取組を見直し、幼児の豊かな経験につなげられるよう実践を重ねてきました。素晴らしい研究実践はたくさんあるのですが、「こどもの日」に関わる取組を紹介します。
「世界で1番大きいこいのぼりって、あるのかな?」
こどもの日に関連して、どの園でも幼児が話し合いながら、工夫してこいのぼり作りをします。それだけでも、立派な活動ですが、本園では「大きなこいのぼりを作れたね」と喜び合う中で、「世界で1番大きいこいのぼり」に興味がわき、みんなで調べることになりました。調べてみると100mのこいのぼりがあることを発見!まだ算数もやっていない幼児ですが、100mを体感するためにメジャーを持ってとなりの枝川小へ!「歩いたら155歩だったよ!」そこから小学校のこいのぼりの大きさを調べたり、本物の鯉の大きさを調べたりするうちに、いろいろな魚の大きさも調べてみました。
「100mのこいのぼりのこと、もっと知りたい!」
幼児は100mのこいのぼりがある埼玉県加須市に、自分たちの知りたいことをたくさん書いた「質問状」を送りました。すると、なんと回答だけでなく、8mと3mのこいのぼりが送られてきました。幼児は大喜びで、すぐに小学校に行ってこいのぼりを揚げたそうです。この経験は、幼児にとっての人とのつながり、学びへのつながりということについても、とても価値のあるものとなりました。「目と口の大きさが、10mもある!」
「ジンベエザメのぼりを作ろう!」
「もっと大きいこいのぼり作ろうよ!」、「鯉じゃなくて、大きくてかっこいいジンベエザメにしようよ!」いろいろな魚を調べたことがここにつながります。私は実際にジンベエザメのぼりを見ましたが、超カッコイイです。ちなみに3m20cmあり、幼児が最初に作ったこいのぼりの3倍以上もあります。何と、クラゲのぼりも作ったそうです。
こいのぼり作りから芽生えた、幼児の興味・関心を先生が認め、ともにわくわくしながらつなげていく支援をしてきたことが、幼児の豊かで素敵な経験となっていきました。
今日の保育の中で、こんなことがありました。手遊びじゃんけんをして、あいこになりました。さっと、次の勝負に行きそうですが。「なかよし~!」と同じものを出したことを互いに喜び合っているのです。年中組でも、年長組でも、先生の温かさに幼児が安心して、伸び伸びと楽しんでいる姿がありました。また、保育室や園庭が素敵な優しい空気に包まれているんです。私はこれまでたくさんの園でたくさんの保育を見てきましたが、いい保育だなあと思うときは、たいてい先生と幼児が見えない糸でつながっているんです。いいクラスだなあと思うときは、幼児と幼児も、みんなが糸でつながっているんです。私は、そう感じています。本園もそうでした。どこにいても、先生と幼児の思いが、みんなの思いが、しっかりつながっていました。
教育においては、「よさや強み」を大切にしがちですが、「苦手や弱み」を受け入れること、それを友達同士で認め合い、励まし合うことで協働につなげていくことが大切で、本園ではそれができていることを講師の先生がお話くださいました。素晴らしいことです。
やっぱり、幼稚園っていいな。先生と幼児の笑顔とわくわく感があふれる、優しい空気に包まれた素敵な1日を過ごさせてもらいました。ありがとうございました。
江東区教育委員会 教育長 本多健一朗
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
