外出時の心得・帰宅困難者対策
外出時の心得
地震が発生したとき、被害を最小限に抑えるには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をとることが大変重要です。
普段とは違った場所や場面というだけでも不安になりますが、落ち着いて行動ができるようにするには、普段から地震に関心を持ち、備えておくことが大切です。
- カバンや上着で頭を保護しましょう。
- 周囲の状況をよく確かめましょう。むやみに動くことは危険です。
- 係員などの指示に従い、落ち着いて行動しましょう。
建物の中にいたときには
- デパート・スーパーでは
ショーケースや商品などから離れ、カバンなどで頭を保護しましょう。係員や館内放送の指示に従い、落ち着いて避難しましょう。 - 劇場・映画館では
シートとシートの間に身を隠し、カバンなどで頭を保護しましょう。あわてて出口に向かうと将棋倒しなどが起きて大変危険です。係員や館内放送の指示に従い、落ち着いて避難しましょう。 - 高層ビルでは
避難のときにエレベーターは絶対に使ってはいけません。エレベーターは停止し、中に閉じ込められるおそれがあります。階段を使って避難しましょう。 - オフィスでは
落下物に気をつけて、ただちに机などの下にもぐりましょう。ロッカーやキャビネットなどの転倒や机上にある機器類の落下にも注意しましょう。 - 作業所では
急いで作業台などの下にもぐりましょう。ただし、大型機械の倒壊や落下、爆発などの危険があるときにはとどまらずに脱出が優先です。 - 学校では
教室の中では、先生の指示に従い、机の下に隠れましょう。廊下にいたら、窓際から離れ、蛍光灯などの落下物に気をつけましょう。校庭にいたら、窓ガラスが割れて落下する危険があるので校舎から離れ、先生の指示を待ちましょう。
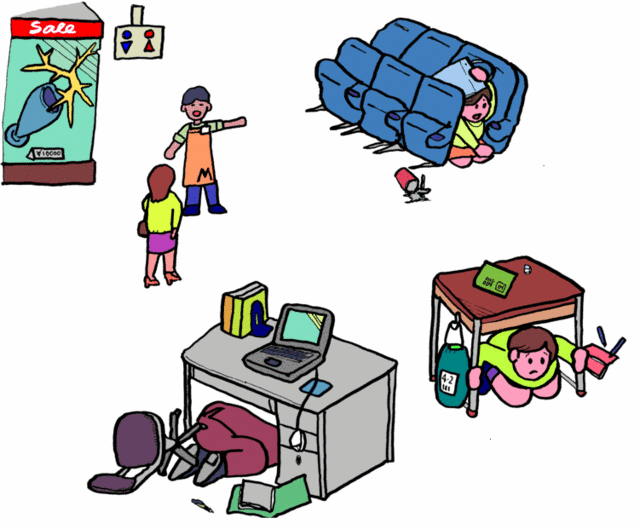
屋外にいたときには
- 街中では
窓ガラスや看板などの落下物に注意し、カバンなどで頭を保護しながら、空き地や公園、学校などに避難します。ブロック塀や自動販売機の転倒、垂れ下がった電線のそばなどには近づかないようにしましょう。 - 地下街では
地下街は、耐震性や防災設備の面では比較的安全な場所ですので、カバンなどで頭を保護しながら、落下物や転倒物の危険性のない壁際で揺れがおさまるまで待機しましょう。パニックなどの混乱が最も危険ですので、係員の指示や誘導灯に従い落ち着いて行動しましょう。 - 電車や地下鉄の車内では
急停車することがありますので、つり革や手すりに両手でしっかりつかまりましょう。途中で停まっても非常口を開けて勝手に外に出たり、窓から飛び降りたりするのは大変危険です。乗務員の指示にしたがって、落ち着いて行動しましょう。 - 車の運転中では
ハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車しましょう。周囲の状況を確認し、カーラジオで正確な情報を入手し、警察官などの指示に従いましょう。大地震のときには、車での避難ができません。避難の必要があるときには、キーをつけたまま、ドアロックもしないで車から離れます。車内には車検証や貴重品を置いておかないようにしましょう。 - 海岸やがけのそばでは
津波の危険があるので、すばやく高台に避難しましょう。津波情報をよく聞き、注意報・警報が解除されるまでは海岸に近づかないようにしましょう。がけのそばでは、落石・土砂崩れの危険があるので、すぐに安全な場所に避難しましょう。
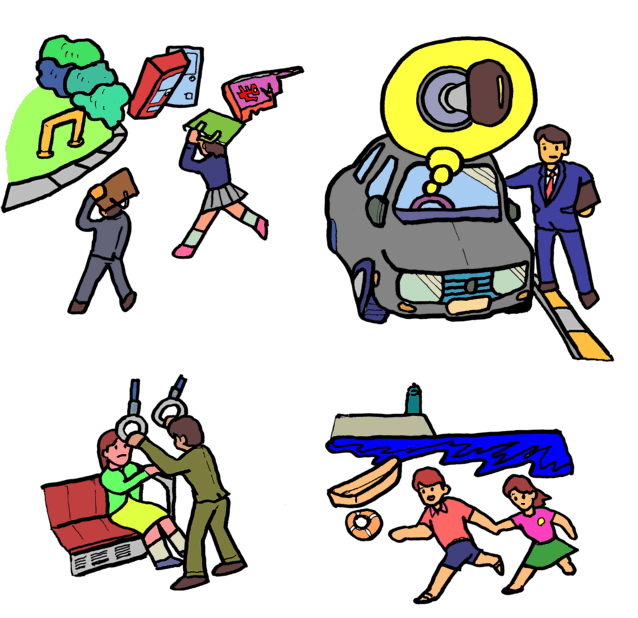
帰宅困難者対策
江東区には、毎日多くの人が通勤・通学などで集まります。
昼間に大地震が発生すると、交通機関が停止し、外出先から自宅に戻ることができない事態が予想されます。無理な帰宅行動は多くの危険を伴う行動であると同時に、混乱の発生により行政の救命・救急活動に支障をきたすおそれがあります。
東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」が平成25年4月に施行され、事業所における従業員の施設内待機や従業員の3日分の備蓄(飲料水・食料等)などが努力義務化されています。帰宅困難に備えることは、企業、学校などの組織の責任ですので、日頃から対応を決めておきましょう。
また、買い物客や行楽客など、行き場のない帰宅困難者の受入施設としては、都立施設などが「一時滞在施設」として指定されています。一時滞在施設に移動した場合にも、混乱が収拾してからの帰宅行動の開始に努めてください。
個人としても日頃から次のようなことを心がけておきましょう。
帰宅困難者心得10か条
- あわてず騒がす、状況確認
- 携帯ラジオをポケットに
- 作っておこう帰宅地図
- ロッカー開けたらスニーカー(防災グッズ)
- 机の中にチョコやキャラメル(簡易食料)
- 事前に家族で話し合い(連絡手段、集合場所)
- 安否確認、災害用伝言ダイヤル等や遠くの親戚
- 歩いて帰る訓練を
- 季節に応じた冷暖準備(携帯カイロやタオルなど)
- 声を掛け合い、助け合おう
災害用伝言サービス
災害時には、安否情報の確認のため、電話がつながりにくくなることが予想されます。そこで、家族や親戚・友人との間で安否確認や避難場所の連絡等を円滑に行うために、次の「災害用伝言サービス」を活用しましょう。
【災害用伝言サービス】
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- 災害用伝言板(web171)
- 災害用伝言板
災害用伝言ダイヤル(171)
利用できる端末
加入電話(プッシュ回線、ダイヤル回線)、公衆電話、ISDN、携帯電話・PHS、IP電話から利用可能です。(詳細はご利用の電話会社にお問い合わせください。)
利用方法
【伝言の録音・再生】
- 「171」をダイヤルします。
- 録音をするときには「1」を、再生をするときには「2」を押します。(暗証番号を利用する録音は「3」を、再生は「4」を押します。)
- 連絡を取りたい被災地の方の電話番号をダイヤルします。
- プッシュ回線は「1」を押します。(ダイヤル回線はダイヤル不要)
- 伝言の録音・再生をします。
以下の期間は体験利用が可能となっていますので、日頃から操作方法を確認しておきましょう。
- 毎月1日,15日0時00分~24時00分
- 正月三が日(1月1日0時00分~1月3日24時00分)
- 防災週間(8月30日9時00分~9月5日17時00分)
- 防災とボランティア週間(1月15日9時00分~1月21日17時00分)

こんなときに171です
災害用伝言板(web171)
利用できる端末
インターネットを利用できる端末(パソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話等)から利用可能です。
利用方法
【伝言の登録・確認】
- 災害用伝言板(web171)(外部サイトへリンク)にアクセスします。
- 連絡をとりたい被災地の方の電話番号を入力します。
- 伝言を登録・確認することができます。(事前に設定することで閲覧者を限定することもできます。)
災害用伝言板
利用できる端末
携帯電話・PHSのインターネットから利用可能です。
利用方法
【伝言の登録】
- 災害用伝言板にアクセスします。(災害時は各社の公式サイトのトップ画面に災害用伝言板の案内が表示されます。体験利用の際はメニューリスト内からアクセスしてください。)
- 「災害用伝言板」の中の「登録」を選択します。(登録は被災地域内の携帯電話・PHSからのアクセスのみが可能です。)
- 現在の状態について「無事です。」等の選択肢から選び、任意で100文字以内のコメントを入力します。(状態の複数選択や、コメントのみの利用も可能です。)
- 「登録」を押して、伝言板への登録が完了となります。
【伝言の確認】
- 災害用伝言板にアクセスします。(伝言の確認はPC等からも行うことができます。)
- 「災害用伝言板」の中の「確認」を選択します。(確認は全国からのアクセスが可能です。)
- 安否を確認したい方の携帯電話・PHS番号を入力し「検索」を押します。
- 伝言一覧が表示されますので、詳細を確認したい伝言を選択してください。
災害用伝言板の詳細については、運営している携帯電話・PHS各社のページをご覧ください。
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

